
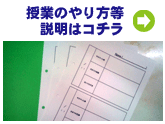
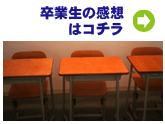
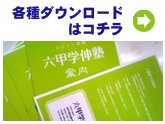
人間力認定協会
の「児童発達支援士」の試験に合格しております。
簡単に説明すると、
ADHDや学習障害など、昨今増えてきているそのような子たちにどのようなアプローチをすれば良いかの勉強をしているという認定になるかと思います。
私自身、子どもたちに勉強を教える仕事を長くしていく上でいろんな経験をしてきましたし、色んな子と接してその中で多くの学びがありました。資格試験のための勉強をすることにより、更に知識を得ることが出来、とても有意義でした。
そのような経験の中で私自身が感じたこと、あくまで私個人の意見ですので「そういった見方もあるか」くらいで読んでいただきたいのですが
私自身、このような子たちを〇〇障害と言うことに少し抵抗があります。
私の中では「走るのが速い・遅い」「球技が得意・苦手」「人と話すのが得意・苦手」などと変わらないものとして接しています。
なので接し方もそれほど変わりません。
得意な部分を伸ばし、苦手な部分をいかに補っていくかなんです。
そのためにはまず「自分が何を出来ていないのか知る」ことが大切だと考えます。そしてそれを「どう克服していくのかを考える」ことが重要なのです。
出来ないことを言われると自己肯定感が下がるという話もよく聞きますが、じゃあ言わない方が良いのか?、自己肯定感が上がるよう勝てるまで努力する方が良いのか?自分が苦手な分野で他の人と勝負して自己肯定感を上げられるほどの結果を求める方が酷だと思いませんか?
だからといって苦手なことは避けても良い、やらなくても良いとはなりません。いかに「少しでも出来るようにするか」というのがポイントです。
まず出来ていないことを知ってもらう。そのために、言い方にはかなり気を遣うべきです。
出来ないことをダメだと言うのではなく、それが苦手なんだということをわかってもらった上でそれを「どうやって少しでも出来るようにするか」そのために「どんなことをやっていかないといけないか」を考えて行動出来るようにさせてあげる必要があるのです。その手助けをしてあげてるようなイメージです。
そのように苦手部分を少しでも克服しながら、自分が好きな部分、得意な部分を伸ばす努力をして
「得意なところで勝てばいいやん」
と思います。
長々と書かせていただきましたが、
塾というものをやっている以上、結果を求めなければいけないのは当然ですが、そこまでに行きつく行動や経過が重要だと考えます。
いくら結果が良くても、それまでのプロセスが良くなければ注意しますし、逆に結果が芳しくなくても努力した内容が良ければ誉めます。
それって結局、学習障害などと診断された子と、されなかった子
どちらに対しても同じことが言えるんじゃないですか。
だから分けて考える必要もないですし、あくまで得意・不得意の範疇なんだと思って接しています。
得意なところを伸ばし、不得意なところを少しでも出来るように努力する。
そのお手伝いをさせていただく塾です。
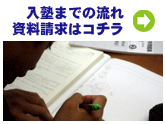


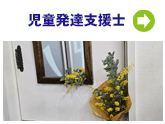
六甲学伸塾(ろっこうがくしんじゅく)
〒657-0067 神戸市灘区篠原本町1丁目7-25 北村ビル1F中店舗 TEL/FAX:078-882-9078
Copyright(C) 2011 RokkoGakushinjuku. All Rights Reserved.
このサイトに掲載している記事・写真等あらゆる素材の無断複写・転載を禁じます。